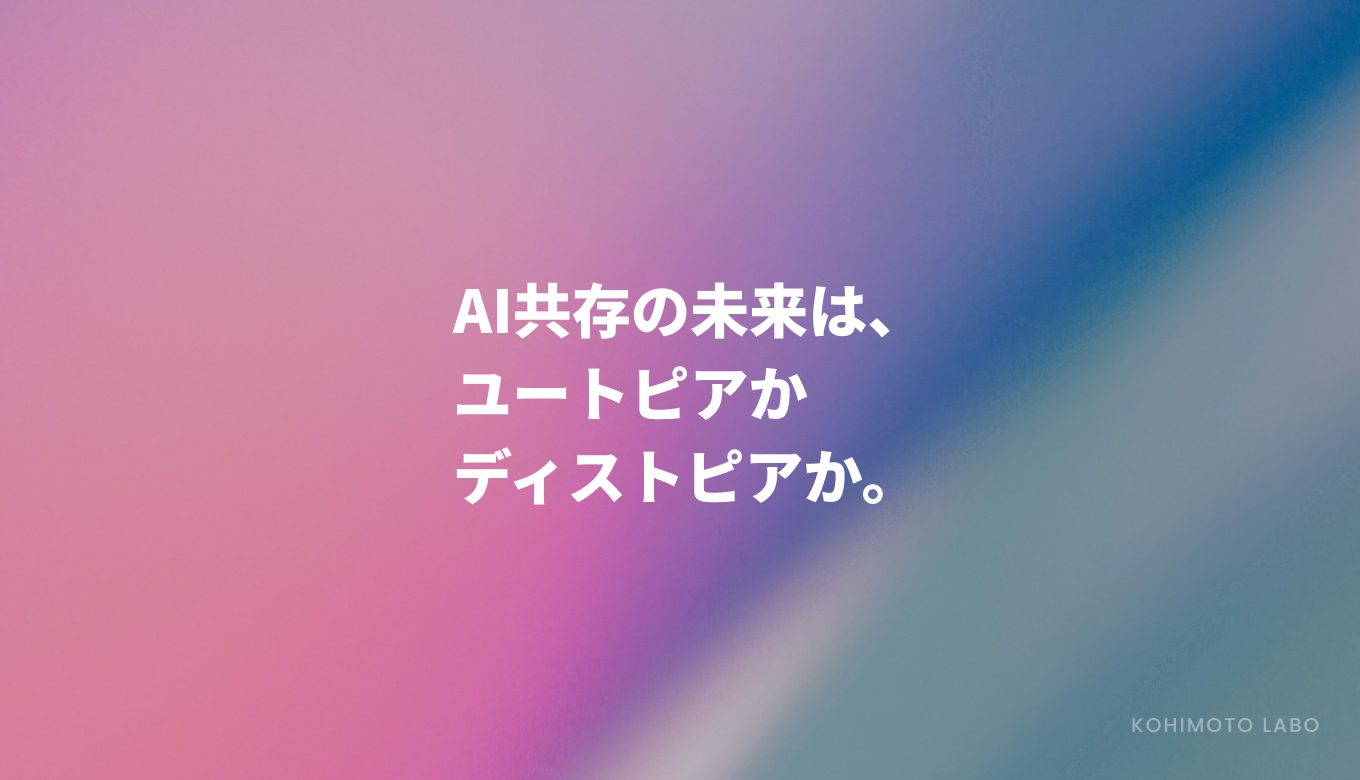
最近、みきちゃんとエンジニアの方と飲んでいた時に「AI共存の未来」について話していたことから派生して
「結局は、AI共存の未来がディストピアかユートピアかみたいな議論は、人の民意次第な気がする。AIで仕事がなくなり、お金がこのまま更に一極集中するか、再分配されてベーシックインカムが確立されるか等、今が、色んな意味で向こう100年の未来の分岐点なのでは・・・?」みたいなことを考えたのでメモします。
多くの人がAIに対して、不安と希望をうっすらと感じていると思います。今のところ、意志や心を持たないAIというテクノロジー自体は中立的なツールです。
私たちは今、その方向性を決める岐路に立っていると思います。
もしAIを「効率化」や「コスト削減」だけの道具として使い続けたらどうなるでしょう。
雇用の大部分は機械に置き換えられ、仕事を失った人々は経済的に追い詰められるかもしれません。
一方で、AIを所有し利益を独占する企業や一部の国家には富が集中し、格差は拡大する。監視と管理のためにAIが使われれば、個人の自由やプライバシーも失われるかもしれません。そして人間の創造性は外注先となり、社会は短期的な最適化に絡め取られていく。また、戦争でAIが活用され、AIそのものの戦闘に対する認知や能力が上がるかもしれません。これは、私たちが望めば容易に到達してしまう未来です。
逆にAIを人を解放する手段として使う事も出来ると思います。
生産性が劇的に向上することで、人は「生きるための労働」から解放される可能性があります。余剰の富を再分配し、ベーシックインカムのような制度が確立されれば、人々は安心して暮らしながら、創造や学び、他者へのケアといった活動に専念できる。労働から自由になった人類は、浮いた時間は、創造・探究・ケア・地域活動といった人間にしかできない営みへ振り向けられる。
テクノロジーが人間を置き換えるのではなく、人間をより人間らしくする。これが一部ではなく全ての人に恩恵があるユートピア的未来です。
再分配などのAIをどう扱うかの制度について、多くは国主導の税と予算が占めると思います。
ですが、未来を決めるのは国家の制度だけではありません。企業や市民レベルでも「再分配」の実験を行う事は可能です。
Patagoniaのように利益を社会や環境に還元する企業もありますし、AIによって削減したコストを労働時間の短縮や給与に還元するモデルも考えられます。
弊社も毎年、売り上げに応じて寄付を行っています。
ステークホルダー資本主義の広がりは、株主至上主義を超えた新しい潮流を示していけます。
日本でも「地域通貨」や「共通マネーポイント」の実験が行われています。さらに、ブロックチェーンを活用したDAO(自律分散型組織)は、参加者全員でAIの成果を分配する可能性を秘めています。クラウドファンディングや市民基金の仕組みも「小さなベーシックインカム」を先行的に実現する手段になり得ます。
この数十年でAIは指数関数的に進化してきました。次の100年、人類社会がどう変わるかは結構今の私達一人一人の意思決定にかかわってくる気がしています。
AIはただの道具にすぎません。そう考えると、ディストピアになるかユートピアになるかは民意がどう舵を切るかに実質かかっていると言えます。
過去の歴史でも全ての技術は作り手ではなく、使い手(過去は権力者が多かった)が決めてきたように、人の意思が反映されます。
国家レベルでの早急な制度改革は、かなり重要だと思いますので、私達ができる事として、まずこの視点も持って選挙へ行く事だと思います。
そして、企業や民間でもお金の使い方を考え、社会善を意識して利益を循環させ、草の根的に分配の仕組みを作っていく事も、もしかしたら可能かも。
もし成果が見えなくても、方向として意識としてそちらに向かう事?その積み重ねが「AI共存のユートピア」を現実のものにしていくヒントがある気がしました💡
民主主義は技術である。どんな技術でもそうだが、民主主義もそれを改善しようと頑張る人が増えると良くなるのだ。
ーオードリー・タン
編集者:Yuka Fujimoto
Webディレクター。美大在学中に、画面ひとつで世界中の人と繋がれるWebの可能性やデザインへ興味を持つ。インターンを経て就職したIT企業で実務経験を積む。肉より魚派🐟
PICK UP